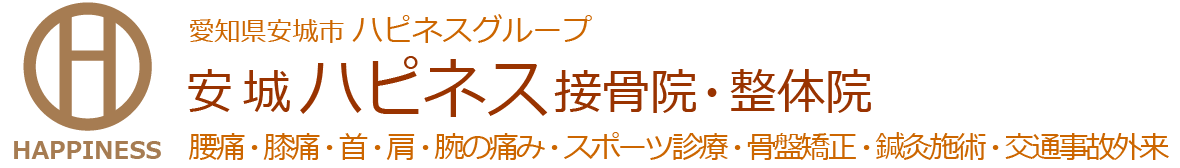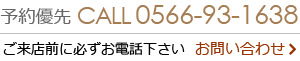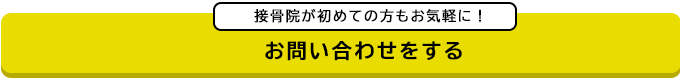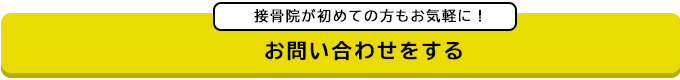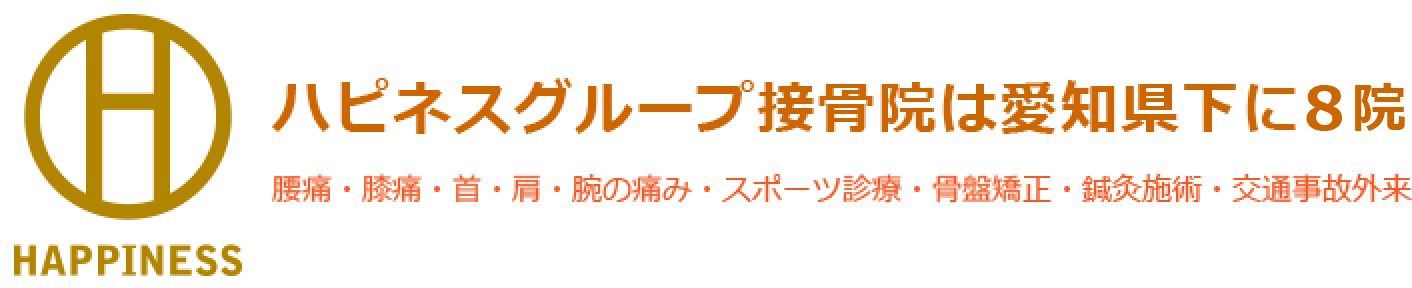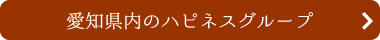こんにちは!安城ハピネス接骨院です。
日常生活の中で「腕が痺れる」「手先がピリピリする」といった症状に悩まされる方は少なくありません。痺れは一時的な血流の滞りで起こることもありますが、繰り返し起こったり長時間続いたりする場合は、体の深い部分に原因が隠れていることもあります。ここでは腕の痺れの代表的な原因についてご紹介します。
1. 首からくる神経の圧迫
首には腕や手へとつながる神経が多数通っています。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で首に負担がかかると、頸椎(首の骨)の間から出る神経が圧迫され、腕や手に痺れを感じることがあります。いわゆる「頸椎症」や「椎間板ヘルニア」が原因となるケースも少なくありません。
2. 肩や胸の筋肉の緊張
腕に向かう神経や血管は、肩や胸の筋肉の間を通っています。猫背や巻き肩など不良姿勢が続くと、大胸筋や小胸筋、斜角筋といった筋肉が硬くなり、神経や血流を圧迫して痺れが出ることがあります。
3. 血流不良
同じ姿勢での作業や冷えによって血流が悪くなると、腕や手先に十分な酸素や栄養が行き届かず、痺れやだるさを感じることがあります。特に寒い季節やエアコンの効いた環境では、血流障害による痺れが出やすくなります。
4. 疾患によるもの
糖尿病や末梢神経障害など、内科的な要因で痺れが出ることもあります。しびれが長引いたり、感覚の低下を伴う場合は医療機関での精密検査が必要です。
接骨院でできること
腕の痺れが筋肉の緊張や姿勢の乱れによって起きている場合、接骨院での施術は有効です。手技療法で筋肉の硬さをほぐし、姿勢改善や骨格矯正によって神経や血流の通り道を整えることで、症状の軽減が期待できます。また、自宅でできるストレッチや生活習慣のアドバイスも併せて行うことで、再発予防にもつながります。
「腕の痺れくらい」と放置してしまうと、慢性的な神経障害に進行する恐れもあります。症状が気になる方は、早めのケアを心がけましょう。
日常生活の中で「腕が痺れる」「手先がピリピリする」といった症状に悩まされる方は少なくありません。痺れは一時的な血流の滞りで起こることもありますが、繰り返し起こったり長時間続いたりする場合は、体の深い部分に原因が隠れていることもあります。ここでは腕の痺れの代表的な原因についてご紹介します。
1. 首からくる神経の圧迫
首には腕や手へとつながる神経が多数通っています。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で首に負担がかかると、頸椎(首の骨)の間から出る神経が圧迫され、腕や手に痺れを感じることがあります。いわゆる「頸椎症」や「椎間板ヘルニア」が原因となるケースも少なくありません。
2. 肩や胸の筋肉の緊張
腕に向かう神経や血管は、肩や胸の筋肉の間を通っています。猫背や巻き肩など不良姿勢が続くと、大胸筋や小胸筋、斜角筋といった筋肉が硬くなり、神経や血流を圧迫して痺れが出ることがあります。
3. 血流不良
同じ姿勢での作業や冷えによって血流が悪くなると、腕や手先に十分な酸素や栄養が行き届かず、痺れやだるさを感じることがあります。特に寒い季節やエアコンの効いた環境では、血流障害による痺れが出やすくなります。
4. 疾患によるもの
糖尿病や末梢神経障害など、内科的な要因で痺れが出ることもあります。しびれが長引いたり、感覚の低下を伴う場合は医療機関での精密検査が必要です。
接骨院でできること
腕の痺れが筋肉の緊張や姿勢の乱れによって起きている場合、接骨院での施術は有効です。手技療法で筋肉の硬さをほぐし、姿勢改善や骨格矯正によって神経や血流の通り道を整えることで、症状の軽減が期待できます。また、自宅でできるストレッチや生活習慣のアドバイスも併せて行うことで、再発予防にもつながります。
「腕の痺れくらい」と放置してしまうと、慢性的な神経障害に進行する恐れもあります。症状が気になる方は、早めのケアを心がけましょう。
接骨院・整体院が初めての方へ
初めて接骨院や整体院に行く場合、どのような流れかわからず不安ではないでしょうか?
ご来店からご退室の流れ
❶ご予約・ご来店
❷問診票記入
❸問診
❹触診・検査・施術提案
❺各種施術
❻症状説明・指導
❼お会計・お見送り
安城ハピネス接骨院・整体院
愛知県安城市住吉町荒曾根1-244
0566-93-1638
#安城市ギックリ腰
#安城市接骨院情報
#安城市ハイボルテージ治療
#安城市骨盤矯正
#安城市テーピング指導
#安城市運動アドバイス
#安城市ハピネス接骨院